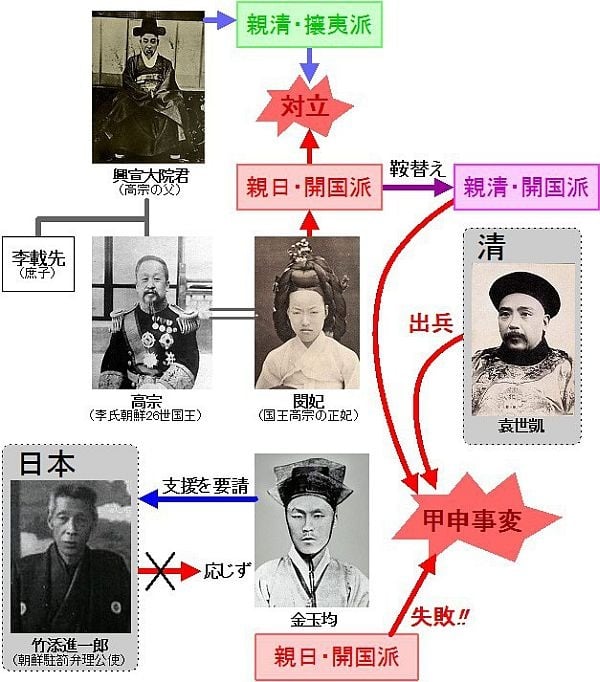闘いの歴史
闘いの記録 (戦争と人間)
単独インタビュー 安倍元首相の銃撃事件当日、翌日の対面を振り返る
政治ジャーナリストで元NHK解説委員の岩田明子さん。故・安倍晋三元首相に“最も食い込んだ記者”として知られている。2002年、当時官房副長官だった安倍元首相の番記者を担当して以来、20年以上に渡って取材をしてきた。だが、22年7月8日に安倍元首相は演説中に銃撃され、亡くなる。あの時、岩田さんは何を思って、どのような対面を果たしたのか、振り返ってもらった。(取材・構成=中村智弘)
安倍さんが銃撃されたという一報は、NHKの関係者から聞きました。ちょうど、永田町に向かって歩いているときです。「安倍さんが撃たれたみたいだが、ちょっと深刻かもしれない」と伝えられました。「まさか、そんなこと」と思いました。
強運の持ち主で、晴れ男。雨の予報であっても現地に赴けば晴れてしまう。絶対に、弾は当たっていないはずだと根拠もなく確信をしていました。すぐに安倍さんの携帯に電話をしましたが、つながりません。ひとまず、渋谷のNHK放送センターに戻ることにしました。
きっと取り込んでいるのだろう。手が空けば、すぐにコールバックがきて「大変だったけど、大丈夫だから!」と電話がくると信じていました。でも、握りしめた携帯には、一向に連絡がこない。報道を見ていると、どんどん深刻な状況になっていて、私は頭が真っ白になりました。動悸(どうき)が激しくなるのが自分でも分かりました。
同行していた秘書に電話したり、他社の記者からも問い合わせや連絡があったりして、情報は錯綜(さくそう)していました。ただ、時間がたつにつれて、周辺の人たちが「とにかく祈ろう」と口にし始めました。私もひたすら祈ることにしました。
亡くなったことを知ったのは、NHKの廊下でした。涙が止まらなかったです。必ず助かると信じていましたから、どうしてこんなことになるのか? と頭が混乱しました。「日本のために」が口癖で、持病を抱えながらもストイックに頑張ってきた一国の指導者が、なぜ選挙期間中にテロで命を落とさなければならないのか。こんな悲劇が起こるはずがないと、現実を受け入れられずにいました。
その日はBS国際報道とラジオジャーナルで、銃撃事件や安倍さんの歩みを解説しました。ラジオジャーナルでは、ジャーナリストの江川昭子さんと対談し、放送後の雑談の中で、江川さんから「眠れないかもしれないけど、食べることと眠ることが大事よ」と声をかけてもらいました。鉛のような体を引きずるようにしてセンターを後にしましたが、とにかくご遺体に対面しなければと思いました。
安倍さんのご遺体が富ヶ谷のご自宅に到着したのは、事件の翌日です。ご自宅には弔問を希望する人が殺到していましたが、夕方に私も対面することができました。心のどこかでは事実を認めたくない自分がいて、死に顔を見てしまったら、立っていられるかどうか自信がありませんでした。
ご自宅では、石原伸晃さんや公明党の太田昭宏さんらとすれ違いましたが、みな号泣していました。室内からは悲痛な声も聞こえてきて、玄関に足を踏み入れた途端、涙が出てきました。
妻・昭恵さんや親族の方と手を握り合うも言葉が出ず、手が震え線香をあげられず
出迎えた妻の昭恵さんや親族の方たちと手を握り合いましたが、私はお悔やみの言葉すら出てきませんでした。部屋に入ると、お母さま(安倍洋子さん)が座っていらっしゃった。憔悴(しょうすい)した表情のお母さまが「ああ、岩田さん」と顔を上げると、「晋三はかわいい子だったわ」とおっしゃいました。
このとき、お母さまの気持ちは、“子どもの頃の半ズボン姿の晋三”と一緒にいるのだ、と感じました。母親が息子に先立たれた悲しみを思うと、本当に辛かったです。私は頭に包帯を巻いて横たわっている安倍さんに、「総理、起きてください」と言おうとしましたが、ほとんど言葉になりませんでした。ただただ涙が出て、数珠を持つ手も震え、線香をあげることもままなりませんでした。
安倍さんはやすらかに眠っていました。その口は、「岩田さん、」と今にも言い出しそうに見えました。そのとき、絶望とはこういう気持ちを表現するのだと実感しました。
しばらくは血圧が上がり、一睡もできない日々が続きました。夢であってほしいと願うのですが、すぐに現実に引き戻されることの繰り返しでした。事件が起きたのは夏でしたが、国葬が終わると、あっという間に秋は深まり、少しずつ日常が戻り、大みそかと元旦が例年と同じようにめぐってきました。
あれだけ大きな存在の人がいなくなっても、時は粛々と流れ、何事もなかったかのように自然はめぐるのだ、と思うととてつもない寂寥(せきりょう)感が込み上げてきました。年が明けてからも、安倍さんがよく訪れたレストランや事務所などに、顔を出したこともありました。もしかして、と思ってのぞき込むのですが、当然、安倍さんの姿は、そこにはありません。
夜の10時から12時は、安倍さんとの“電話タイム”でした。それは20年間、ずっと続けてきました。この時間帯は、安倍さん自身も「情報収集の時間」に決めていて、いろいろな方面に電話をしていたようです。
私はガラケーとスマホ両方持っているのですが、安倍さんはガラケーの方に電話をかけてきました。そもそも記者として、いつでもどんな取材先からも電話を取り損ねたくなかったので、新しい服を購入したときには、必ずガラケーが収まるポケットを作っていました。でも、もうこの時間帯に携帯が鳴ることはありません。
安倍さんとのやり取りで心に残っているのは、第2次安倍内閣が退陣した後のこと。私とのやりとりの中で、台湾海峡をめぐる問題や、国際情勢を考えると、将来的に、第3次安倍内閣の待望論が出てくるのではないかという話になりました。そのとき、安倍さんは「天が望めば」と口にしました。私欲ではなく、最後まで政治家として、人生を全うしようとしているのだと感じました。頭の中では、いつも日本のため、世界のためを考えている、根っからの政治家だったと思います。
□岩田明子(いわた・あきこ)千葉県船橋市出身。1996年、NHKに入局。岡山放送局へ配属。2000年、東京放送センター報道局政治部へ異動、官邸記者クラブ所属。02年、当時官房副長官だった安倍晋三元首相の番記者を担当し、以来、20年以上に渡って安倍元首相を取材。08年、外務省記者クラブに所属、北朝鮮問題を担当。09年、政権交代を経て鳩山由紀夫内閣の菅直人副首相の担当を務める。13年、NHK解説委員室へ異動、政治担当の解説委員と政治部の記者職を兼務。22年7月、NHKを退局、ジャーナリストとして報道番組に出演する一方で、月刊誌や専門誌などで執筆活動も続けている。趣味は昭和歌謡。現在は母親と二人暮らしで、介護に奮闘中。千葉大学客員教授・中京大学客員教授。中村智弘