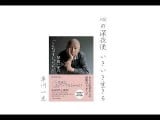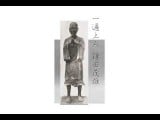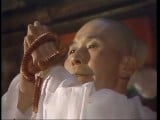ヨキヒトの仰せ
お釈迦様の生涯と教え
心の深夜便 いきいき生きる 早川一光
一遍上人 鎌田茂雄
酒井雄哉大阿闍梨
「成道会(じょうどうえ)」―釈尊が悟りを開かれた日
「成道会(じょうどうえ)」―釈尊が悟りを開かれた日
釈尊の生涯に深く関連する日のひとつが、12月8日です。
この日は何の日ですかとお尋ねすると、「太平洋戦争開戦の日=真珠湾攻撃の日」「ジョン・レノンが亡くなった日(今年は40年目を迎えます)」、あるいは地方によっては「針供養の日」という答えが返ってきます。「お釈迦様がお悟り(さとり)を開かれた日でしたね」というお答えは、ご門徒の皆さんからもなかなか出てきません。12月を迎えるとともに、街はクリスマス一色となり、ますます「成道会」の存在は、かき消されてしまうようです。
およそ2500年前、東北インドにあった小国「シャカ国」の王子シッダールタは、地位・財産・名誉など私たちが欲するすべてのものに恵まれ、何不自由なく過ごしていました。しかし、老人や病人さらには死人との出遇いをとおして、人として生まれた以上、老・病・死からまぬがれることができないという「わが身の事実」に気づき、思い悩みながら、真の幸せとは何かと深く考えていました。
その時、出家をし、質素な身なりながらも、心身を制御しながら善につとめ心穏やかな境地を求める生き方に励む「沙門」と出遇いました。29才のとき、意を決してお城を出て、修行生活に入りました。もちろんお城は大騒ぎ。沙門となった王子を見つけたマガダ国王ビンビサーラは、財や軍隊をあげるから国に戻ってはと申し出ましたが、「私はこの生活を楽しんでいます」といって、その申し出を断っています。
シッダールタは、師をみつけて瞑想の方法を学びましたが、その境地には満足せず、5人の仲間とともに断食をはじめとする厳しい苦行を続けましたが、求める境地にはいたることができず、修行を放棄します。ほぼ骨と皮だらけの体を河に入って清め、ふらふらと歩いている苦行者を見た村娘スジャーターは、神様に捧げようとして持っていた乳粥を彼に与えました(この娘の名がコーヒーに入れるミルク製品名になっています)。元気を回復したシッダールタは、近くにある大きな樹(ピッパラ樹)の下に座し、深い瞑想に入りました。
その時、彼の前に悪魔(マーラ)が現れます。武器や雨風で襲いかかり、あるいは美しい女性を登場させて誘惑をしたり、あらゆる手段を用いて邪魔をしました。このマーラの襲来は、内面の様々な欲望との闘いや苦行を棄てたことへのうしろめたさを表しているといわれます。しかし、悪魔の襲来を降伏(降魔)され12月8日の明け方、明けの明星が輝くなか、悟り(बोधि, bodhi:菩提)を得られ、ブッダ(बुद्ध, Buddha)「目覚めたもの」となられました。この出来事を「降魔成道」といいます。お城を出て6年目、シッダールタ35才の時のことです。以後、ブッダ(仏陀)と呼ばれます。
瞑想に入られた大きな樹は後に「菩提樹」と呼ばれるようになりました。また、悟りを得られた場所は、ブッダガヤとよばれ仏教聖地の一つとして世界中から仏教徒がお参りに来られます。現在この地には、52メートルの大塔が建っており、世界遺産となっています。
「さとり」とは何か。どのようなことに「目覚められた」のかは、またいずれ。
仏を仏たらしめた法というものは
Facebook Yasuda Rizinさん曰く
発明したのなら法とは言わないのです。
釈迦仏が出遇った。
見出した。
作ったのではないのです。
そういう真理がある。
真理といっても理論的な真理という意味ではない。
本来的な真理です。
われわれが忘れていた真理です